沖縄史の一断面、『琉球処分』。その語られ方には、なぜか拭いがたい違和感がつきまとう。
今回は、国が激動の渦に飲まれる中、全く異なる未来を見つめた二人の琉球エリートに焦点を当て、その違和感の正体を探る旅に出たい。
序章:前提としての処分
1879年(明治12年)、明治政府は国最後の王・尚泰を東京へ移住させ、軍と警察の力を背景に琉球藩の廃止と沖縄県の設置を断行した。これが「琉球処分」である。近代日本の形成期、全国の藩を県へと変えた「廃藩置県」の最後の仕上げであった。
この時、政府の全権代表として琉球に乗り込んだのが、処分官・松田道之だ。彼は懐柔と圧力を巧みに使い分け、明治政府の方針を冷徹に執行する「実行者」の役割を全うした。
さて、私たちは「琉球処分」と聞いて、どのような印象を抱くだろうか。「処分」という言葉の響きは、あまりに一方的で高圧的だ。あたかも、平和な独立国であった琉球を日本が理不尽に併合したかのような──。
だが、ここに最初の「違和感」が生まれる。当時の行政用語として「処分」とは「物事を処理し、最終決定を下す」という、より中立的な事務手続きを指す言葉でもあったのだ。
もちろん、言葉の解釈一つで、この歴史の重みが変わるわけではない。国家の決断と、言葉の裏に隠された意味。その狭間で、琉球は深刻な対立と、困難な選択を迫られた。
次章では、その渦の中心にいた対照的な二人の人物の運命を追うことで、この巨大な歴史の謎の中心へと、さらに深く潜っていきたい。
第1章:悲劇の忠臣・林世功
琉球国の首都・那覇に、久米村(クニンダ)と呼ばれる特別な場所があった。そこは、国最高の学府・明倫堂を擁し 、中国との外交と学術を担うエリート層が暮らすコミュニティであった 。
本章の主人公、林世功(りん せいこう、1842-1880)は、まさにこの久米村が生んだ俊英である 。14世紀に中国・福建省(古称:閩)から渡ってきた職能集団「閩人三十六姓」の末裔として 、彼は幼少期から中国の言語と文化に精通し、祖国・琉球の外交を担うことを運命づけられていた 。
林世功の世界観は、この環境そのものによって形成された。明倫堂で儒教の経典と外交術を学び 、彼の精神は、琉球の主権と文化的アイデンティティの基盤である中国との数世紀にわたる冊封・進貢関係を絶対視する価値観の中で育まれたのである 。
その類まれな才能は若くして開花し、官費留学生として北京の最高学府で学んだ後 、彼の出世街道は約束されたものであった。帰国後、瞬く間に昇進を重ね、ついに国の世継ぎである尚典の教育係に抜擢される 。それは、将来、国最高の顧問官「国師」の座へと至る道であった 。
しかし、彼の栄達の瞬間こそが、国家の悲劇の始まりと重なってしまう。林世功が輝かしい未来を掴みかけていたその時、明治日本の巨大な力が、国の土台そのものを静かに、しかし組織的に解体し始めていたのだ。後に「琉球処分」と呼ばれる、抗いがたい歴史の渦である 。
悲劇への序曲
しかし、彼の栄達の瞬間こそが、国家の悲劇の始まりと重なってしまう。林世功が輝かしい未来を掴みかけていたその時、明治日本の巨大な力が、国の土台そのものを静かに、しかし組織的に解体し始めていたのだ 。
1875年、日本政府の特使・松田道之が琉球王府に乗り込み、清への朝貢停止など、琉球の主権を事実上無効にする最後通牒を突きつける 。この圧力に、王府、そして林世功ら久米村のエリート層は激しく揺さぶられた。中国との繋がりこそが、彼らの存在意義そのものであったからだ 。
最後の抵抗
もはやこれまでと判断した国王尚泰とその大臣たちは、宗主国である清に救国を嘆願すべく、密使を派遣することを決断する。使節団の責任者は、国王の義兄でもある重臣・幸地親方朝常(こうちうぇーかたちょうじょう)。そして、その完璧な中国語能力と学識を買われ、請願書の通訳官という重責を担ったのが、林世功であった 。
だが、彼らが頼った清国は、もはや往時の威光を失っていた。彼らの必死の嘆願に対し、清政府が返したのは「情と理をもって反論する」という口先だけの支援と、北京への上京を禁ずる命令だけだった 。
それでも、林世功たちは諦めなかった。彼らは二つの異なる言葉を使い分ける、絶望的な二正面作戦を展開する。清に対しては「忠誠」「恩義」「正義」という儒教的な道徳言語で訴え 、アメリカやフランスなど西欧列強には「主権」「国際法」「条約」という近代的な法言語で理を説いた 。
殉国の賦
その彼らに、最後にして最悪の知らせが届く。日清間の妥協案として、琉球を南北に分割する「分島問題」が浮上したのだ 。宮古・八重山諸島を清国に割譲する代わりに、沖縄本島以北の日本領有を認めるという案であった 。
故郷が、まるで物のように切り分けられる──。その知らせに、林世功は慄然とした。彼にとって領土の分割は、国家の完全な消滅と同義だった 。
1880年11月20日、条約調印が目前に迫る中、林世功は最後の請願書を清国の総理衙門に提出し、涙ながらに国の復興を訴えた 。そして、その場で自らの命を絶った 。38歳であった 。
彼の懐には、二首の辞世の句が遺されていた。その一首は、彼の心境を完璧に映し出している。
古来忠孝幾人全、憂国思家已五年。 一死猶期存社稷、高堂専賴弟兄賢。
> (古来、忠義と孝行を全うできた者が幾人いるだろうか。国を憂い、家族を思ってから早五年。この一死をもって、なお国家の存続を願う。故郷の両親のことは、賢明な弟たちに託すしかない)
第2章:現実主義の悲劇・宜湾朝保
林世功が、中国との繋がりを宿命づけられた外交エリートであったとすれば、本章の主人公、宜湾朝保(ぎわん ちょうほ、1823-1876)は、琉球の「王道」を歩んだエリートであった。1823年、王都首里の名門・向氏宜湾殿内(しょううじ ぎわんどぅんち)に生を受ける。この家系は、王族の分家である小禄御殿(おろくうどぅん)の支流にあたり、国の中でも屈指の名家であった。
琉球の貴族として、彼の教育は本質的に多文化的であった。外交の基礎となる漢学、日本の文化や政治を理解するための和文学、そして琉球固有の学問や芸術。彼は三つの文化圏の知を自在に吸収した。
特に彼の知的形成に決定的な役割を果たしたのは、日本の古典文学、とりわけ『万葉集』への傾倒であった。当初は父に命じられ、嫌々読み始めたものの、やがて彼はその中に、古代日本語と自らの話す琉球の言葉との、驚くべき言語的類似性を見出す。例えば、顔を「つらかまし」、嘘を「よこし」と呼ぶなど、『万葉集』の古語が、琉球の日常に息づいていることを発見したのである。
この発見は、単なる知的好奇心にとどまらなかった。それは彼の政治的姿勢の知的基盤を形成したのだ。彼の親日的傾向は、明治政府の圧力に屈した単なる現実判断ではなく、琉球と日本が文化的に、そして言語的に一つの祖先を共有しているという、若き日に形成された深い信念に根差していた。この「失われた同胞」という物語こそ、彼が後に日本の宗主権を受け入れる際の、強力なイデオロギー的根拠となったのである。
その信念を裏付けるかのように、彼のキャリアは二つの大国と直接向き合う経験によって磨かれていく。30歳の時、進貢使節として清国へ渡り、北京に至るという大役を担う。そして帰国するや否や、今度は琉球を実質的に支配していた薩摩藩へ赴き、当代随一の英明な藩主・島津斉彬に謁見するよう命じられたのだ。この薩摩滞在中に、彼は歌人の八田知紀(はった とものり)ら日本の知識人たちと重要な関係を築いている。
この清国と薩摩への相次ぐ派遣は、宜湾に、琉球の存立を左右する二大勢力を直接比較分析する、またとない機会を与えた。壮大だが儀礼的で、西欧の力に衰えを見せる清国の現実。そして、小さいながらも産業と軍事力に活気あふれる日本の潜在能力。この経験こそが、彼の現実主義的な地政学認識を研ぎ澄ませる決定的な要因となった。
危機管理者の登場
1862年、フランスまで巻き込んだ政界スキャンダル「牧志・恩河事件」の混乱の最中、宜湾はその冷静な実務能力を買われ、国最高の行政職である三司官に任命される 。この国を揺るがす大事件に、彼は巧みな交渉術で対処し、「危機管理者」としての評価を確立した 。
そして、彼は琉球国最大の危機、「琉球処分」と対峙することになる。
明治維新後、宜湾は新政府への祝賀使節団の副使として東京へ派遣された 。そこで彼らが受け取ったのが、琉球国を廃し「琉球藩」を設置するという天皇の詔勅であった 。
伝えられるところによれば、宜湾はこの結果を「喜んで帰国した」という 。ある解釈では、これを薩摩の直接支配から脱する好機と見た、とされている 。しかし、彼の人生の軌跡を追う我々には、別の心境が見えてくる。『万葉集』の中に「失われた同胞」を見出した彼にとって、この「琉球藩」設置は、ついに同胞との再統合を果たす、信念の成就と感じられたのではないだろうか。
二つの正義の衝突
だが、宜湾の信念に基づく決断は、琉球国内に激しい亀裂を生んだ。
同じく三司官であった亀川盛武(かめがわせいぶ)が率いる「頑固党」は、断固として親清国の立場をとった 。彼らにとって、清との関係を断つことは、数世紀にわたる伝統と忠誠への裏切りであり、到底受け入れられるものではなかった。彼らの戦略は、日本の要求に徹底抵抗し、宗主国・清に介入を求めること。前章の主人公、林世功もまた、この勢力の一員であった 。
親日か、親清か。近代化か、伝統か。二つの「正義」が激しく衝突する中で、宜湾は全ての責任を追及されるスケープゴートとされていく。頑固党の激しい突き上げと、彼らによって火をつけられた民衆の非難を一身に受け、1875年、彼は三司官の職を辞任せざるを得なくなった 。
そして翌1876年、失意のうちに54歳でその生涯を閉じた 。彼が自らの信念と引き換えに受け入れた「琉球藩」が、完全に解体され「沖縄県」となる悲劇の最終幕を見ることなく、彼はこの世を去ったのである 。
終章:『羹に懲りて膾を吹く』— 私たちの歴史の「物語」と、その処方箋
ここまで、私たちは『琉球処分』という歴史の渦に翻弄された、対照的な二人のエリートの運命を追ってきた。
一人は、中華世界への忠誠に殉じた、林世功。 もう一人は、日本との文化的な同根に未来を賭した、宜湾朝保。
彼らが、それぞれの出自と経験から生まれた揺るぎない「信念」に基づき、その人生を一貫して生きてきた様が見えたはずだ。
しかし、『琉球処分』の物語は、彼らの死をもって終わらなかった。大東亜戦争の敗戦後、日本の歴史観が大きく転換する中で、この出来事には全く新しい、戦後独自の「物語」が与えられ、語り継がれていくことになる。
それは、戦争という熱い「羹」に懲りた社会が、自らの歴史という「膾」を吹き始めた時に生まれた物語でもあった。
戦前の軍国主義と帝国主義への強烈な反省から、戦後の日本では、日本の「加害の歴史」を直視する大きな潮流が生まれた。その文脈において、「琉球処分」は、日本がアイヌモシリ(北海道)や台湾、朝鮮へと拡大していく帝国主義の「最初のステップ」として位置づけられたのだ。平和な交易国家であった琉球を、武力を背景に併合したという解釈は、日本の「過ちの歴史」を象徴する格好の事例となった。
この新しい「物語」の中で、二人の主人公の役割もまた、書き換えられていく。
- 林世功は、巨大な日本の力に屈しない、悲劇の愛国者として、その抵抗精神が称賛された。
- 宜湾朝保は、国を売り渡した協力者という単純な評価から、近代化を受け入れた先見性のある現実主義者として再評価され、さらには、板挟みの中で苦悩した悲劇の責任者という、より複雑な姿で描かれるようになった。
この、歴史の事実を特定の価値観で再構成する動きこそ、私たちが旅の初めに感じた「違和感」の正体であり、社会全体が陥った、ある「思考のクセ」の現れだったのである。
そのクセを、先人たちは的確な諺で言い表している。「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」と。
一度熱い吸い物で火傷をした者は、冷たい和え物までフーフーと吹いて冷まそうとしてしまう。これは単なる用心深さではない。過去の強烈なトラウマによって、脳の危機管理システムが正常な判断力を失い、本来危険ではないものまで「脅威」と誤認してしまう、痛々しい後遺症の姿だ。
戦争という未曾有の「羹」によって心に深い火傷を負った私たちは、戦後、「国家」や「愛国心」、「伝統」といった、羹の「器」に似たもの全てを「膾」として過剰に警戒し、遠ざけようとしてきたのかもしれない。
では、このトラウマ的な連鎖を断ち切り、未来へと進むために、私たちは何をすべきなのか。その処方箋は、個人の心の回復プロセスの中にこそ見出すことができる。
第一の処方箋は、「安全の再確認」である。 火傷の痛みは、決して忘れず、その事実を真正面から受け止める。しかし同時に、「あの時と今とでは状況が違う。私たちは今、安全な場所にいる」と、現在地を繰り返し確認するのだ。過去の亡霊に、現在の私たちを支配させてはならない。
第二の処方箋は、「羹と膾の徹底的な分析」である。 私たちを傷つけたのは、「器」そのものではない。「器」に入っていた「熱」こそが、痛みの本質だ。感情的な恐怖に理性の光を当て、私たちを破局へと導いたものが何だったのかを精密に分析する。狂信、排他性、人権の無視…。その危険な「熱」を含まない健全な「膾」まで、恐れる必要はないのだと、自らの知性で理解することだ。
そして最後の処方箋は、「新しい物語の創造」である。 分析によって安全を確認できたら、勇気を持って「膾」に箸を伸ばしてみる。小さな成功体験を一つひとつ積み重ね、心と体を再教育していく。そうして、「私たちはトラウマの奴隷ではなく、過去から学び、未来を選択できる主体なのだ」という、新しい自己の物語を、自らの手で紡ぎ直していく。
これは、個人にとっても、社会にとっても、容易な道ではない。しかし、この知的な勇気と自己への誠実さこそが、私たちを過去の呪縛から解き放つ唯一の道なのだ。

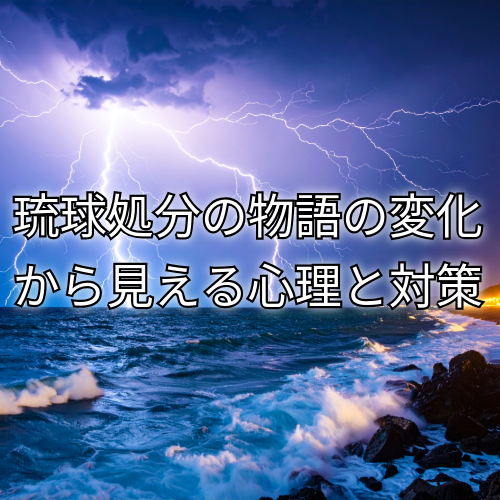


コメント