第1章:理想家の藩主と、天才のパートナー
19世紀半ば、欧米列強の影がアジアに迫る中、日本の南端・薩摩藩に、時代の遥か先を見つめる一人の藩主がいた。第28代当主、島津斉彬(しまづ なりあきら)。彼は、このままでは日本が西洋の植民地になりかねないという強い危機感を抱き、蒸気船や電信、ガラス製造などを手掛ける日本初の近代洋式工場群「集成館事業」を推進する、当代随一の理想家であり、改革者であった 。
斉彬の夢は、薩摩一国の繁栄に留まらなかった。彼は、薩摩の力で幕政を改革し、日本全体を強く生まれ変わらせるという、壮大な野望を抱いていた。だが、その野望を実現するには、幕府の厳しい監視を潜り抜け、海外の知識や技術を直接手に入れるための、特別な「窓」が必要だった。
その時、斉彬の目に飛び込んできたのが、琉球の一人の役人だった。
その男の名は、牧志朝忠(まきし ちょうちゅう)。 1853年、ペリー艦隊が琉球に来航した際、彼は公式な通訳として交渉の最前線に立った。牧志は、独学で身につけたという英語、さらにはフランス語、中国語を巧みに操り、アメリカ側と堂々と渡り合った。その卓越した語学力と、物怖じしない国際感覚は、交渉を監視していた薩摩の役人を通じて、斉彬の知るところとなる。
斉彬は、牧志の中に、自らの夢を実現するための「鍵」を見出した。 幕府の支配下にありながら、中国との朝貢関係も持ち、西洋との窓口ともなる琉球。そして、その琉球にあって、西洋と対等に渡り合える唯一無二の才能を持つ牧志朝忠。
ここに、日本の歴史を動かしかねない、強力なパートナーシップが誕生する。藩主・斉彬の壮大な「構想」と、天才役人・牧志の類まれな「実務能力」。身分も生まれた場所も違う二人は、日本の未来を憂い、近代化を志すという一点において、固く結びついた。
そして二人は、琉球を舞台に、幕府の度肝を抜く、ある壮大な秘密計画に着手するのである。
第2章:幕府を動かす秘策
島津斉彬の近代化構想において、最大の障壁は、硬直化した江戸幕府の体制そのものであった。諸藩の力を削ぐための「武家諸法度」は、大名が巨大な軍艦を保有することを厳しく禁じており、これが日本の海防を致命的に遅らせていた。
しかし、その幕府中枢に、斉彬と志を同じくする、たった一人の盟友がいた。老中首座・阿部正弘である。
阿部は、斉彬の卓越した国際感覚と危機感を深く理解し、日本の未来のためには、薩摩のような先進的な雄藩の力が必要不可欠だと考えていた。だが、幕府内の保守派や他の大名の抵抗は根強く、正面から軍備近代化を進めることは不可能だった。
そこで、斉彬と阿部は、旧体制の岩盤を打ち破るため、一つの「共謀」とも言える秘策に打って出る。それが、琉球国を隠れ蓑として、フランスから最新式の蒸気軍艦を購入するという計画であった。
この密計の仕組みは、こうだ。 まず、琉球が薩摩藩から資金を借り入れる。その資金で、牧志朝忠がフランス側と直接交渉し、軍艦を購入する。そして、納入された軍艦の所有者は、あくまで琉球国とする。その上で、その船を薩摩藩が借り受け、実質的に自藩の軍事力として運用する──。
この計画は、表向きには「幕府を欺く」という形をとりながら、その実態は、幕府の最高責任者である阿部正弘の暗黙の了解のもと、日本の未来のために、あえて法を乗り越えようとする超法規的な国家改造計画であった。
そして、この国家レベルの壮大な「共謀」の実行役として、白羽の矢が立ったのが、琉球の天才役人・牧志朝忠だったのである。
第3章:二つの星、墜つ
日本の中心(江戸)と周縁(薩摩・琉球)が、一人の天才役人・牧志朝忠を介して連動する──。日本の未来を賭けた壮大な国家改造計画は、今まさに、その第一歩を踏み出そうとしていた。
しかし、歴史の女神は、彼らに微笑まなかった。
1857年夏、この計画の最大の理解者であり、幕府中枢の要であった盟友・阿部正弘が、39歳の若さで急死する。日本の舵取りを担う改革派の巨星が、あまりにも早く墜ちたのだ。
この報せは、島津斉彬に大きな衝撃を与えた。幕府内における最大の「盾」を失ったことで、計画の遂行には、より一層の慎重さと覚悟が求められることになった。
だが、本当の悲劇は、そのわずか1年後に訪れる。
1858年7月、日本を未曾有のコレラが襲う中、斉彬もまた病に倒れ、この世を去ってしまう。享年50。琉球の軍艦購入計画の進捗を、誰よりも心待ちにしていた矢先のことであった。
阿部正弘、そして島津斉彬。 日本の未来を憂い、身分や立場を超えて手を結んだ二つの巨星が、相次いで墜落した。この瞬間、日本の歴史を動かすはずだった巨大な歯車は、その回転を止め、逆流を始める。
最強の庇護者二人を同時に失った牧志朝忠の頭上に、そして琉球の未来に、暗い雲が急速に垂れ込めてきていた。
第4章:粛清の嵐
島津斉彬の死は、薩摩藩の権力構造を根底から覆した。 藩主の座は、斉彬の遺言により息子の茂久が継いだが、幼い藩主の後見人として実権を握ったのは、斉彬とは長年対立してきた異母弟、島津久光(しまづ ひさみつ)であった。
久光は、兄・斉彬の急進的な近代化政策を「藩の財政を傾かせるだけの無謀な浪費」と断じ、その方針をことごとく覆していく。蒸気船も、大砲も、ガラス工場も、兄が夢見た未来の全てが、久光にとっては過去の負債でしかなかった。
そして、この薩摩藩の「逆コース」の嵐は、真っ先に琉球へと吹き付けた。
斉彬の庇護のもと、異例の出世を遂げた牧志朝忠。彼は、久光ら新体制派から見れば、「兄・斉彬の負の遺産の象徴」そのものであった。斉彬派を一掃し、藩の主導権を完全に掌握するため、彼らは牧志をスケープゴートに、琉球に潜む「斉彬の残党狩り」を開始する。
薩摩の新体制派と結びついた琉球国内の反・牧志派は、これを好機と捉えた。彼らは、フランス軍艦の秘密購入計画を「国を危うくする独断専行」であり、「薩摩と組んで王家を廃し、琉球を乗っ取ろうとした大逆無道の陰謀」であると告発した。
1859年、牧志朝忠、そして彼の計画を支持した上司の恩河朝恒らは、収賄や国王廃立の謀反容疑で次々と逮捕される。かつて国の英雄と目された天才役人は、一夜にして「国賊」の汚名を着せられ、囚われの身となったのだ。
拷問を含む厳しい尋問が始まり、牧志は心身ともに極限まで追い詰められていく。彼が夢見た近代国家への道は、無残にも閉ざされ、暗く冷たい牢獄の中、ただ死を待つだけの絶望的な日々が始まった。
第5章:禍福は糾える縄の如し
国賊の汚名を着せられ、牢獄に囚われた牧志朝忠。1862年、薩摩への護送の道中、彼は謎の死を遂げた。公式記録では自決とされるが、その死には暗殺の黒い噂が絶えない。享年44。
琉球が生んだ不世出の天才は、こうして歴史の舞台から退場させられた。そして、彼と共に、「あり得たかもしれない、もう一つの日本の未来」もまた、永遠に失われた。
ここから先は、想像力の領域である。もし、阿部正弘と島津斉彬が夭逝せず、牧志と共に軍艦購入計画が成功していたら、日本の歴史はどう変わっていただろうか。
おそらく、薩長同盟も、倒幕運動も、血で血を洗う戊辰戦争も起こらなかっただろう。日本は徳川幕府を頂点とする幕藩体制を維持したまま、斉彬や阿部といった開明的な指導者の下で、より穏健な「上からの近代化」を成し遂げていたかもしれない。
その世界では、中央集権国家を目指した「廃藩置県」も、その延長線上にある強硬な「琉球処分」も、史実と同じ形では起こり得ない。近代化し、自信をつけた「徳川日本」にとって、琉球は無理に併合すべき「県」ではなく、むしろ中国や西洋との独自のパイプを持つ特別な交易・外交拠点として、その地位を維持し続けた方が、遥かに価値があっただろう。横浜や長崎とは別に、日本が持つもう一つの「特別外交ルート」として、琉球国は存続し続けたかもしれない。
それは、内乱の混乱を避けられた、一見すると「より良い未来」に思える。
しかし、本当にそうだろうか。
この「穏健な近代化」ルートには、もう一つの、より暗い結末も予測できる。 史実の日本が、英国と日英同盟を結び、強大なロシア帝国の南下を防ぐことができたのは、日清・日露戦争での勝利によって、その国力と軍事力を世界に証明したからに他ならない。このIFの世界でフランスとの関係を強固にした日本が、果たしてイギリスと手を結ぶことができただろうか。
幕藩体制を維持した日本の近代化は、薩長が断行した急進的な改革よりも、ペースが遅かったかもしれない。その日本に、ロシアの圧倒的な圧力に抗する力はあっただろうか。
もしかしたら、そのIFの世界では、日本は内乱こそ避けられたものの、列強の圧力の前に屈し、北方の領土を奪われ、あるいは国全体がその影響下に置かれるという、「より最悪な未来」を迎えていた可能性すらある。
何が幸福で、何が不幸か。それは、複雑に絡み合った一本の縄のようであり、歴史のその時点では、誰にも知ることはできない。
今この瞬間に嘆いている、あなたへ。 もしかしたら、その苦しい現状こそが、未来をより良くするための、大いなる種になっているのかもしれない。

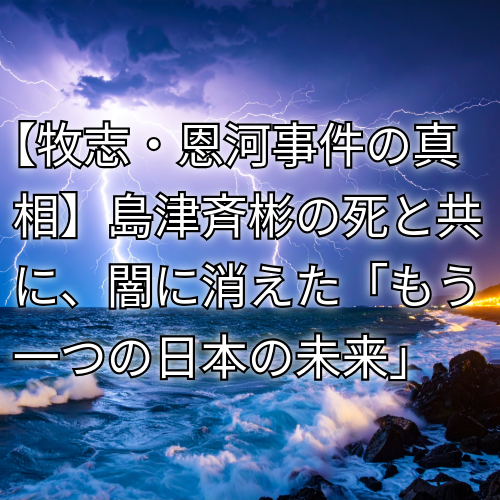


コメント