序章:トルストイの問いから、私たちの問いへ
「戦争と平和」――文豪レフ・トルストイがその長大な物語に冠したこの言葉ほど、二つの概念を不可分な対として、私たちの心に刻み込んだものはないかもしれない。平和とは、戦争のない状態である。この自明に思える定義は、しかし、本当に世界の真理を捉えているのだろうか。
砲火の轟音が止み、兵士たちが故郷へ帰還すれば、そこに訪れるのは真の「平和」なのだろうか。私たちは、この古くて新しい問いの探求に、あえて異なる角度から光を当てたい。その入り口は、こうだ。
「平和の対義語は、本当に戦争だろうか?――あるいは、その本質は、もっと根源的な『混沌』にあるのではないか?」
この問いを羅針盤として、私たちは「平和」という名の、壮大で終わりのない旅路へと出発する。
第1章:秩序としての平和――混沌との戦い
17世紀の哲学者トマス・ホッブズは、国家なき自然状態を「万人の万人に対する闘争」と描いた。そこは、死の恐怖が常に付きまとう、永続的な戦争状態、すなわち「混沌」の世界だ。人々はこの耐えがたい恐怖から逃れるため、自らの自由の一部を主権者に譲渡し、強力な権力によって「秩序」を構築することを選んだ。彼にとって、平和とはまさに、この混沌を克服した「秩序ある状態」に他ならなかった。
歴史を紐解けば、その巨大な実例が姿を現す。「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」だ。ローマ帝国は、圧倒的な軍事力を背景に、地中海世界に200年以上の長きにわたる「平和」をもたらした。帝国に逆らう者には容赦ない「直接的暴力」が加えられたが、その支配下では、たしかに大規模な戦争は鳴りを潜め、交易は栄えた。
この「戦争や直接的暴力が存在しない状態」を、現代平和学の父、ヨハン・ガルトゥングは「消極的平和」と呼んだ。それは、平和を考える上での最低限の条件であり、第一歩である。しかし、私たちの旅は、ここで終わりはしない。
第2章:正義としての平和――見えざる暴力との対峙
パクス・ロマーナの下で、属州の民は本当に「平和」だったのだろうか。ローマ市民の繁栄の陰で、重税に苦しみ、搾取され、その文化や自由を抑圧されていた人々にとって、それは「平和」という名の支配ではなかったか。
ここで、私たちは旅の第二の問いに直面する。「秩序さえあれば、そこは本当に『平和』なのだろうか?」
ガルトゥングは、この問いに「否」と答える。彼は、目に見える「直接的暴力」だけでなく、社会の仕組みそのものに組み込まれた「構造的暴力」の存在を暴き出した。貧困、差別、不正義、格差――これらは、特定の誰かが銃を向けなくとも、静かに、しかし確実に人々の命や可能性を奪う「見えざる暴力」だ。
この「構造的暴力」さえも取り除かれ、社会的な正義が積極的に実現されている状態こそ、彼が提唱した「積極的平和」である。
興味深いことに、この思想は古代の叡智と深く共鳴している。ヘブライ語の「シャローム」は、単に争いがない状態を意味しない。「正義」「完全性」「繁栄」「健全な関係性」といった、望ましいものすべてが満たされた、祝福された状態を指す。新約聖書で用いられるギリシャ語の「エイレーネー」もまた、この豊かな思想を受け継いでいる。
見えざる暴力を乗り越え、真の「正義」を社会に打ち立てること。平和への旅は、より深く、困難な領域へと足を踏み入れる。
第3章:『人間の安全保障』――国家の責務と、個人の応答
旅のレンズを、さらに現代へと向けてみよう。2003年のイラク戦争。アメリカは戦争の当事国でありながら、その本土が戦場になることはなかった。多くのアメリカ市民は、爆撃の恐怖とは無縁の日常を送っていた。そこには「消極的平和」と、揺るぎない「国家の安全保障」が存在した。
しかし、その平和は誰のためのものだったのか。ここで、私たちの旅路を照らす第三の光、「人間の安全保障」という概念が登場する。これは、安全保障の主体を「国家」から「一人ひとりの人間」へと転換する考え方だ。すべての人々が「恐怖」と「欠乏」から解放され、尊厳ある生を全うする権利。それこそが、守られるべき核心である。
このレンズを通して見れば、構図は一変する。アメリカという国家の安全は保たれる一方で、その軍事行動によって、イラクに住む無数の人々の「人間の安全保障」は、徹底的に破壊されていた。国内の平和が、国外の非平和を前提として成り立つ。この構造を、私たちは「平和」と呼ぶことができるのだろうか。
しかし、この「国家から個人へ」という視点転換だけで、物語は終わらない。国家の役割は、あくまで安全という「器」を築き、守ることまでである。一人ひとりの内面にある「平和」の形は千差万別であり、国家がそれを一つの型にはめようとすることは、新たな暴力となりかねないからだ。
ここで言う「公共の福祉への貢献」とは、社会の空気に従うことではない。むしろ、法と他者への配慮という共通のルールを守りながら、一人ひとりが自らの信じる豊かな人生を、自由に追求すること。その多様な生き方それ自体が、社会全体を豊かにし、真の「公共の福祉」を育むのである。真の平和とは、保護されるだけの状態ではなく、保護された個人が、その自由を謳歌し、かつ互いの自由を尊重しあう、生命的な循環の中にこそあるのかもしれない。
結論:『創造する平和』へ――私たちの答えと、終わらない旅路
旅の終わり、私たちは出発点の問いへと戻る。「平和の対義語は何か?」
答えは、一つではなかった。それは時に「混沌」であり、「直接的暴力」であり、そして、より根深く、見えざる「構造的暴力(不正義)」であり、「人間の安全保障」が脅かされる一切の状態であった。
では、一体誰が、この複雑で多層的な平和を「構築」するのか。
私たちの旅がたどり着いた答えは、シンプルでありながら、希望に満ちている。それは、国家と個人の「共創」である。
国家は、法と制度によって、国民を暴力や欠乏から守る、頑丈で公正な「器」を築く、第一の建築家だ。 そして個人は、その器の中で、ただ守られるだけでなく、自らの自由を追求し、他者を尊重し、社会に関わることで、平和な日常という「中身」を日々創造し続ける、第二の建築家なのだ。
どれほど立派な家も、そこに住む人々の笑い声、時に流す涙、そして日々の温かな営みがなければ、ただの建物のままで「家庭」にはならない。平和もまた同じだ。国家が築いた頑丈な土台の上で、私たち一人ひとりが自由を謳歌し、互いを尊重し、社会を創り続けて初めて、それは生きたものとなる。
この終わらない「共創」の営みこそ、私たちが『創造する平和』と名付けたものの正体である。そして、その創造を担う力こそ、自らの社会の矛盾を直視する「自覚」と、まだ見ぬ未来を構想する「想像力」に他ならない。

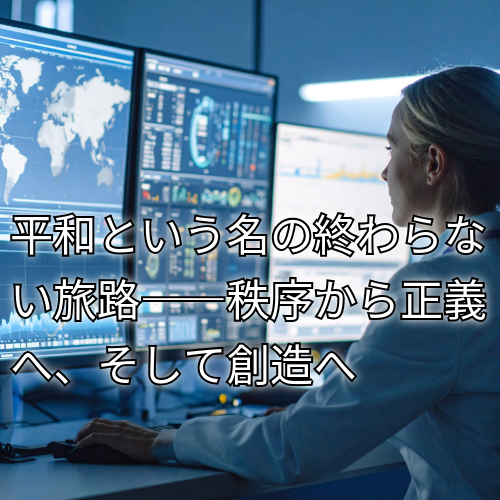


コメント